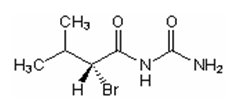
4.1 ヒ素
ヒ素は鉄鋼のようなねずみ色の結晶性粉末で、金属のような外観を持ち、ニンニク臭、毒性が強い。ヒ素の酸化物の一つに亜ヒ酸(三酸化二ヒ素)があり毒物に指定されている。亜ヒ酸は無味無臭のため、毒殺によく利用された。他の利用例としては、医薬品、染料、殺鼠剤、殺虫剤、除草剤、印刷用インク、毒ガスなどが挙げられる。特に、ヒ素が分子内に導入された医薬品としてサルバルサン(606号)がある。この薬はエールリッヒと秦佐八郎によって開発された薬で、梅毒の特効薬であった。
4.1.1 毒性
ヒ素の毒性は、無機誘導体か有機誘導体かヒ化水素化によりそれぞれ異なる。無機誘導体とは無水亜ヒ酸、亜ヒ酸カリウム、亜ヒ酸ナトリウムなどである。中毒の症状は、慢性または急性によって異なり、また吸入か摂取かによっても異なる。ここでは、毒性が特に強い無機誘導体についてみていきたい。
毒物として注目されてきた無機ヒ素化合物、亜ヒ酸のLD50(ラット)は15mg/kg、ヒトの致死量は100~300mgと推定されている。ヒ素は酵素のSH基と結びついて酵素の働きを阻害する。その結果見られる急性中毒の症状として、まず初期段階では嘔吐、血性下痢、激しい腹痛などの胃腸障害、頻脈、血圧低下、呼吸低下、呼吸麻痺などがある。やや遅れて、腎不全、黄疸、末梢神経炎などの症状がある。1998年夏に
一方、慢性中毒の場合は、非常に多様な様相を呈する。症状として、全身の倦怠感、皮膚の角化・色素異常、気管支炎、多発性神経炎などがある。多発性神経炎の中で最も多く見られるものは、視神経障害を伴う重度の知覚異常が挙げられる。中国、インド、タイ、バングラデシュなど世界各地に、現在でも多くの慢性ヒ素中毒者がおり、その数は百万人を超えるものと推定されている。その原因の多くは、これらの地域で1.0mg/lにものぼる高濃度のヒ素を含む地下水を飲料水としていることによるものである。また、慢性ヒ素中毒の一部は鉱山周辺の住民にもみられる。日本では、
4.1.2 治療法
急性ヒ素中毒の解毒剤としてBAL(バル)が有名である。バルはヒ素を分子中に有する糜爛性の毒ガスのルイサルト剤に対処するためにつくられたものである。ルイサイト剤は第一次世界大戦末期にアメリカで発明・開発され、発明者のルイス大尉の名をとってルイサイトと呼ばれている。日本でも、1930年以降
4.1.3 毒は薬
中国の医学についてふれた最古の書物は、紀元前三~四世紀ごろに成立したといわれる『周礼』であるとされている。もともとは儒教経典の一つであるが、その中に「五毒」という記載がある。そして、「およそ医師として病を治すには五毒を集め、これをうまく使いこなさなければならない」と書かれている。つまり、人間を病気にするような悪霊を追い払うには、五毒のような強い効力をもったものでなければならない、というのがその根本思想である。だから、五毒はいずれもヒ素や水銀、硫酸銅、酸化鉄などを含む鉱物性の毒である。つまり、当時の人たちにとって、毒こそが病気(悪霊)に打ち勝つために必要な、しかし、実は危険な薬だったのである。
4.1.4 小説の中のヒ素
ヒ素(正確には、亜ヒ酸)は、毒殺の手段として昔から頻繁に使用された。その影響を受け、小説の中にもよくヒ素が登場する。ここでは、その一例を紹介したい。
1983年のクリスマスの日、フランスである殺人事件が起こった。それが、当時フランス犯罪史上でも例をみないぐらい有名になったマリー・キャベルの事件である。マリーはヒ素を使って夫を毒殺した疑いで終身刑となる。しかし、マリーの犯罪と断定する決定的な証拠は最後まで出なかった。マリーがヒ素を買ったことは断定できたものの、実際の使用目的は殺鼠のためであり、専門家による分析によっても死体からの毒物の検出がなかったのである。ただひとり、当時有名な毒物学者オルフィラが微量の毒を検出したと言ったにすぎなかった。このため世論も真二つにわかれた。
この事件をモデルに書かれたのが小説『ボバリー夫人』(フローベル作、1857年)である。ボバリー夫人はヒ素で自殺をしてしまう。このヒ素は鼠を殺すために使うからといって、オメー氏の薬局の助手ジュスタンをだまして盗み出したものである。この小説のなかで特徴的なのは、ボバリー夫人の生々しい毒死の状況の描写である。描写が詳細で具体的であることからして、フローベルがマリー・キャベルの事件に大変興味をいだいていたことは明白である。
さらに、この小説を意識して書かれたものに『テレーズ・デスケルウ』(モーリヤック作、1927年)がある。テレーズは自分でヒ素を盛ったわけではないが、夫が貧血の治療のために始めたヒ素剤の飲用を、あるとき、自分で間違えて二倍量を飲んでしまった。それをテレーザがわざとだまって見逃したのである。夫ベルナールの死因に疑いをもった医師や薬剤師に告訴されるが、結局、免訴となり帰ってクロロホルムを飲んで自殺しようとする。しかし、突然事件が起こり果たされないという筋である。
いずれにしても、現代小説の中で毒の扱いがだんだん専門的になっていくことが見て取れる。これを機にヒ素など毒物を扱った小説をよんでみるのもよいかもしれない。
参考
歴史を変えた毒 山崎幹夫
毒の科学 船山信次
毒に科学QA 水谷民雄
毒殺 上野正彦
毒の文化史 杉山二郎
医学大事典 森岡恭彦
4.2 睡眠薬
「睡眠薬」の正式名称は「催眠鎮静剤」や「睡眠導入剤」という。不眠症の治療薬として最初に開発されたのはバルビツール酸系や非バルビツール酸系の睡眠薬であった。これらの薬の効果は強いが、呼吸抑制などの中枢神経系にはたらくので、習慣性や大量の服用により死に至る危険性があった。しかし、現在使用されているベンゾジアゼピン系睡眠剤は極端な乱用をしないかぎりは依存の危険性も少なく、安全性の高い優れた薬といえる。
睡眠薬は、大きく3種類に分けられる。
|
バルビツール酸系 |
大脳皮質や脳幹の自律神経中枢のほぼ全域を鎮静化し、入眠へ導く。効果は強いが意識を維持する役割を担う脳の網様体賦活系や呼吸をコントロールする延髄を抑制するので、多量に用いると昏睡に陥ったり、呼吸停止を引き起こしたりして死に至る危険性がある。依存性や副作用が大きい。大量摂取による中毒では、深い昏睡状態に陥り、呼吸緩徐や血圧低下をまねいて、肺浮腫や呼吸麻痺で死亡することが多い。慢性中毒としては、不安、食欲不振、脱力感、幻覚、てんかん様発作があり、モルヒネと同等の習慣性がある。現在は重症な場合を除き、処方されることはほとんど無い。 |
|
非バルビツール酸系 |
バルビツール酸系を改良したもの。耐性や安全性に問題の多いバルビツール酸系に変わるものとして使われてきたが、近年はより安全なベンゾジアゼピン系がこれにとってかわり、処方される機会は少なくなった。 |
|
ベンゾジアゾピン系 |
元々は安定剤として開発された薬のうち、睡眠効果の高いものが睡眠薬に分類される。ベンゾジアゼピン作動(情動をコントロールする中脳の辺縁系に選択的にはたらきかけて中枢神経の活動を抑制する)により、不安や緊張などを取り除き、自然に近い入眠へ導く。入眠効果が自然で依存性や副作用が少ないことから、現在一番処方されている種別である。ベンゾジアゼピン系の中毒としては、嘔吐、悪心、筋力低下、呼吸抑制、錯乱、頻脈、痙攣等があるが比較的に安全な薬剤である。しかし、筋弛緩作用があるため高齢者などに使用する場合、夜間に起きると転倒しやすい。同じベンゾジアゼピン作動性のチエノジアゼピン系・シクロピロロン系もこの種類に含む。 |
また、睡眠薬は作用時間がさまざまで、病態に応じて選択できる。
|
超短時間型 |
15〜30分くらいで効果が現れ、持続時間も短い。主に入眠障害時(寝付けない状態など)に使用される。 |
|
短時間型 |
15〜60分くらいで効果が現れ、持続時間はやや短い。主に中途覚醒時(夜中によく目が覚める状態など)や入眠障害時に使用される。 |
|
中間型 |
30〜60分くらいで効果が現れ、持続時間はやや長い。主に早朝覚醒時(朝早く目が覚めてしまう状態など)や中途覚醒時に使用される。朝起きるのが少し辛い事もある。 |
|
長時間型 |
穏やかに効果が現れ、長時間効果も持続する。神経症や鬱病などが原因の場合、昼間の緊張感や不安感の緩和にも効果を現す。 |
4.2.1 事件に使われた睡眠薬の例
ブロムワレリル尿素(ブロバリン、α-bromoisovalerylurea、bromisovalum、 bromvalerylurea)(非バルビツール酸系)
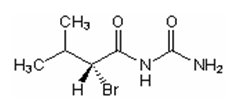
太宰治の「人間失格」に登場する睡眠薬カルモチンの成分である。実際に彼はこれを飲んで自殺しようとしたことがあり、金子みすゞは大量服用により自殺した。古くから催眠鎮静剤として用いられており,催眠鎮静薬や解熱鎮痛薬の成分として配合されて一般薬(OTC薬)としても販売されている.入手の容易さから,現在でもブロムワレリル尿素による中毒はわが国の代表的な薬物中毒の一つであり、自殺の手段として用いられることがある。死因は呼吸中枢麻痺による呼吸停止である。
効果と特徴
1907年にSoamが初めて合成した。1908年から市販されている鎮静、抗痙攣、抗てんかん、抗神経症、睡眠薬である。無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末でにおいはなく、味はわずかに苦い。フェノチアジン系、バルビツール酸系、アルコールなどと併用すると作用が増強される。大量の水と服用した場合には吸収性が増して毒性が強くなる。
毒性
ブロムワレリル尿素の極量は個人差があるが1回2g、1日3gで、経口成人中毒量は3g~6g、経口成人致死量は20〜30gといわれている。致死量のブロムワレリル尿素を服用した際の最高血液中濃度は100μg/ml以上と考えられるが,代謝が早いため、明らかにブロムワレリル尿素による中毒死であると考えられる場合でも血液中濃度がそれほど高くないことがある。重篤な症状(昏睡)の出現する血液中濃度は50μg/ml以上である。
人間にもたらす効果
経口摂取されたブロムワレリル尿素は消化管から速やかに吸収され、効果が発現するまでの時間は20〜30分である.肝臓で代謝されて代謝物を生成するとともに、臭素を遊離する。分解が早いため速やかに血液中濃度が減少するが、大量に服用すると酸性の胃液中で不溶性の塊を形成して持続的に薬剤の吸収が起こることがある。代謝によって遊離した臭素は全身に分布し、長期間服用すると臭素の中毒症状が現れる。排泄は主に尿から行われる。
体内に入るとどうなるのか
症状は、ブロムワレリル尿素以外に臭素および活性代謝産物の濃度に影響され、時間の経過や1回摂取か連続摂取かによっても変わってくる。重症例での症状としては、意識障害や急性循環不全が認められ、意識障害が高度の場合には舌根沈下や呼吸抑制が生じて死にいたる。また、吐物による窒息や嚥下性肺炎の合併も生じる可能性がある。ブロムワレリル尿素はX線透過性が悪いので、服用量が多い場合には腹部単純X線で薬剤の塊が写ることがある。連用により薬物依存、大量・連用中の急な減量・中止により禁断症状、発疹、紅斑、かゆみ、悪心、嘔吐、下痢、頭痛、めまい、ふらつき、知覚異常、難聴、興奮、運動失調、抑うつ、構音障害、発熱を生じることがある。
治療法
ブロムワレリル尿素と臭素の両方への対処を考慮に入れる必要がある。アセトアミノフェンを含有する場合はこれにも注意しなければならない。しかし、1回摂取の急性中毒の場合は臭素が問題となることは少ない。胃内に錠剤や粉末が多量に残存している場合が多いので、胃洗浄などの初期治療を忠実かつ確実に行う必要がある。また,吸収されたブロムワレリル尿素の排泄促進には強制的な利尿が効果的で、利尿薬を投与して尿量を3〜6ml/kg/hrとする。致死量以上を服用した場合や、保存的治療にもかかわらず臨床症状が悪化する場合には活性炭血液吸着法や血液透析などの血液浄化法を行うこともあるが、中枢神経抑制だけならば気道の確保を中心とする保存的対症療法を行う。慢性の臭素中毒の治療に塩化物を投与する方法もある。意識があるときには、大量の水と食塩1〜3gを1時間ごと最低1日6g経口投与、意識のない時には生理食塩水の点滴を行う。塩素が臭素の排泄を促進する。
含まれている商品例
(医療薬)
・ブロバリン末,錠
・ブロムワレリル尿素末
(一般薬)
・リスロンS
・ウット
・ナロン錠
他にも、1998年に起きた「ドクター・キリコ事件」の被害者の1人や芥川龍之介が自殺に用いたと言われるバルビタール(バルビツール酸系)、服用した妊婦の一部に四肢の欠損や耳の障害などの奇形をもつ新生児が誕生したサリドマイドなど、重大な被害をもたらす睡眠薬もあるので注意をして服用しなければならない。
4.3 青酸
青酸は、カール・ウイルヘルム・スチールによって発見された化合物で、炭素と窒素とが結合したシアン(CN-)とプロトン(H+)が結びついているというきわめてシンプルな構造をしている。しかしながら、その毒性は200~300ppmでほとんどの動物が死ぬほどの猛毒である。また、青酸は水溶性ではあるが、常温で気体であるため扱いが難しく、発見者であるカール・ウイルヘルム・スチールも実験中に誤って青酸を吸って死亡している。
過去の事件や推理小説などによく見られる青酸は、一般にどくとしてよく知られているが毒として意外にも様々なところで使われている。たとえば、不純物が混じった中から純金を取り出したり、メッキとして工業的に使われたりしている。そのほかにも殺虫剤、殺鼠剤、金属の研磨剤、電気メッキ溶液、写真工程などにも使われていたりする。
4.3.1 作用メカニズム
シアン(青酸)の人体に体に対する作用メカニズムは、細胞の中にあるミトコンドリアのシトクローム酸化酵素の3価の鉄イオンと結合して細胞の呼吸を阻害することである。そのため、細胞の中の呼吸が阻害されて、体は低酸素状態に陥り、急激な機能停止となる。そして、酸素不足が脳に来ると、呼吸が抑制され、痙攣がおき、呼吸停止となる。事件などでよく用いられる青酸カリは、胃に入ると胃酸によって青酸を発生させるためにどくとして働く。また、シアン化水素酸は、シアン化水素を水に溶かしたものであるが、これはきわめて危険で皮膚についただけでも体内に入る。特に粘膜から体内に入りやすく、そのために死亡に至らしめることが多い。青酸塩類(青酸カリ、青酸ソーダ)の致死量は経口摂取で200~300mg、青酸の致死量は50mgとされている。
4.3.2 青酸による特徴
青酸によって生じる症状は以下の4つである。
① 中毒症状
激しい頭痛、動機、眩暈、胸の苦しさ、呼吸の切迫、呼吸の不整状態による呼吸困難、
さらには、呼吸が停止する。重症な場合、意識不明のまま全身麻痺となり、拍動が停止し、そのまま死に至る。
② 血色
青酸はヘモグロビンと反応してシアノヘモグロビンを形成するため、血液が鮮やかな赤色となる。また、それにより顔や皮膚が赤みを帯びることになる。
ヘモグロビン中のFeイオンに特定の場所で酸素が結合・脱離する事で呼吸が成立する(つまり肺で酸素と結合して様々な場所で酸素が切り離され細胞内に取り込まれることが呼吸である)。しかし、青酸カリの青酸イオン(C≡N-)はヘモグロビン中のFeイオンに結合してしまう。しかも、その結合は酸素と結合した場合よりも非常に強いために、この結合が解けるには非常にエネルギーが必要となるため、生体内では自分で外す事はできず、自然に離れていくのを非常に気長に待つしかない。そのためヘモグロビンが酸素を取り入れることができなくなり、呼吸障害を起こすのである。
③ 胃
青酸は強いアルカリ性であるため、胃粘膜がおかされ、壊死をおこす。そのため、解剖したときに胃壁が赤や褐色となっている。
④ 臭い
青酸カリは、独特のアーモンド臭を漂わせる。
4.3.3 青酸中毒の解毒方法
青酸中毒になった場合は、以下の手順によって治療することができる。
① 酸素(100%)吸入を速やかに行う(呼吸をしていなかったら人工呼吸を行う)
② 亜硝酸アルミを吸入させる。
③ 3%亜硝酸ナトリウム10mlを静注する(3分間で)
④ 25%チオ硫酸ナトリウム50mlを静注する(10分以上で)
⑤ 以上で効果がなかったら③、④の半分をもう一度行う。
次にこれらの手順が効果的な理由を説明する。
まず、シアン化物によって細胞が酸欠状態となるので酸素の吸入を行う(①)。次に亜硝酸エステルや亜硝酸塩で酸化させるとヘモグロビンがメトヘモグロビンへと変化する。このメトヘモグロビンはシアン化物イオンと結合することができる。それによって、シトクロムオキシダ-ゼ戸結合するシアン化物イオンが減少し、細胞の酸欠を軽減させる(②、③)。チオ硫酸塩はシアン化物イオンを無毒なチオシアン化物イオンにかえてしまい、体外に排出させることができる(④)。
アメリカでは、イーライ・リリー社から「シアン化物用具」という商品が出ており、亜硝酸ペンチル、亜硝酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウムが含まれている。
4.3.4 青酸を用いた事件の例
1977年1月4日
昭和52年1月3日午後11時過ぎ、新幹線のビュッフェ(食堂車)でアルバイトをしている男子高校生A君(当時16歳)が同僚と勤務を終えて品川の従業員寮に戻る途中、品川駅と寮の400メートルの間にある電話ボックスにコーラが置かれていたのを発見した。中身は入っており栓もしていたため誰かが忘れたのだろうという軽い気持ちでコーラを持ち帰った。4日午前12時過ぎ同僚達はビール、A君は拾ったコーラを飲んだ。約5分後、A君は急に苦しみだして嘔吐。病院に運ばれたが、午前7時30分に死亡した。
同日の4日午後、その電話ボックスから600m離れた場所で無職の男性(当時47歳)が死んでいるのを通行人が発見。そばにはコーラのビンが転がっていた。東京は、正月気分から一気に冷め戦慄がはしった。また、北品川の赤電話にもコーラ瓶が置かれていたが、拾った中学生は飲まなかったため一命を取り留めた。
警察の調査で、コーラには致死にいたる青酸ナトリウムが混入されていた。警察は、不特定多数の無差別殺人として大掛かりな捜査を開始した。青酸ナトリウムが入手しやすい塗装業や加工業など徹底的に捜査したが、物的証拠に乏しく平成4年に時効が成立した。
事件当時、コカコーラの販売を自粛するスーパやお店が多数にのぼり、コーラ会社も大打撃を受けた
大阪で飛び火
東京の青酸コーラ事件から40日後の2月13日の朝、大阪の会社員・Bさん(当時38歳)が出勤途中、酒屋の前でコーラを拾い飲んだところ意識不明になった。また現場近くの電話ボックスにもコーラが一本置かれていた。警察が調査したところ、この二本のコーラから青酸化合物が発見された。
Bさんは、3日後に退院したがその後、自宅でガス自殺した。40日前の《青酸コーラ事件》が日本中で大騒ぎしていた中で、何故拾ったコーラを飲んだのか?何故自殺したのか?その謎は永久に分からなくなった。
1977年2月14日
昭和52年2月14日午後4時頃、会社経営のAさん(当時43歳)が東京駅八重洲の地下街を歩いていたところ、階段の下にショッピングバッグが置かれているのを発見した。中身を見るとグリコのチョコレート40箱が入っていた。当日はバレンタインデーであり誰かが置き忘れたのだろうと思ったAさんは、そのまま行き過ぎようとしたが先月の「青酸コーラ事件」を思い出し《もし、毒が入っていたら大変なことになる》と近くの交番に届けた。
交番は落し物として処理したが、落とし主が現われないため10日後にメーカである江崎グリコ東京支店に返却した。
受け取ったグリコ東京支店は、チョコの箱に記載されている製造番号を確認しようとしたところ、製造番号が削り取られていたこと、箱を包んでいるセロファンが破れていることに不審を抱いた東京支店は、大阪にあるグリコ本社の研究所に送り分析を依頼した。
この結果、40箱の内4箱の1粒、合計4粒(一箱10粒入り)に致死量の0.3グラムの青酸ナトリウムが検出された。
グリコから警察に届けられて「無差別殺人事件」として捜査が始まった。この40箱の1箱の裏に《オコレルミニクイニホンシンニテンチュウヲクタス/おごれる醜い日本人に天誅をくだす、という意味か》という犯行声明が記載されていた。
第二の犯行
同じ14日、東京駅から一駅の神田駅トイレで会社員のBさん(当時34歳)はチョコレートを拾った。電車でこのチョコレートを食べたBさんは意識不明となり、秋葉原駅から救急車で病院に運ばれた。病院は食中毒と診断し、幸い意識が戻ったBさんは翌日退院した。
ところで、東京駅で発見された青酸チョコレート事件と神田で発生したBさんの事件は、当時は結びつかなかった。Bさんの場合、食中毒として診断されていたため警察にも届けはなかったのである。
が、翌年の昭和53年に捜査本部が事件の洗出しを行った際、神田事件の情報が捜査本部に入り、Bさんから提出されていたチョコレートの分析を行った。その結果、微量の青酸ナトリウムが検出された。
ここで、初めて東京駅と神田駅の事件が繋がった。さらに、聞き込みで2月14日以前にもチョコレートが入ったバックを東京駅の地下街で目撃したという証言者が多数でてきた。捜査本部は、東京駅、神田駅の青酸チョコレート事件と1月の青酸コーラ事件は同一犯人の疑いも睨みつつ大掛かりな捜査をしたが、ついに犯人検挙は出来なかった。